🍀数字に心
🍀税に愛
🍀人生には笑いと熱き想いを
🍀税に愛
🍀人生には笑いと熱き想いを
【25】利益は出ているのにどうしてお金が残らないの?(勘定合って銭足らず)
2025/01/25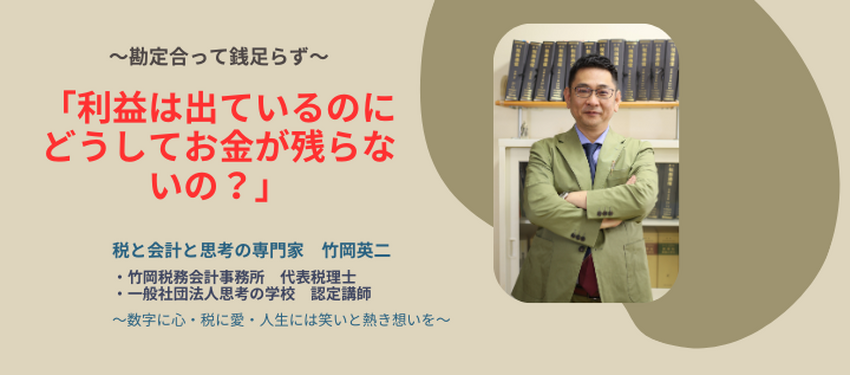
決算書や試算表では利益が出ているのに、お金は残っていない・・・。
しかも、お金はナイというのに、
利益が出ているから、という理由で
法人税や所得税を払わないとイケナイってか!!
どうも解せない・・・。
こういったご経験・ご感想を持っておられる方は
結構多いのではないかと思います。
この「どうも解せない」という感情は、
「損益法」という考え方と
「財産法」という考え方との【違い】に
その端を発します。
損益法の代表例は
会社が払う法人税や個人事業主が払う所得税です。
法人税法や所得税法は
売上から経費を差し引いた利益に対して
課税する仕組みになっています。
よって、極端な話、
100億円の売上があったとしても、
その売上の全額がツケ(売掛金といいます)になっていて、
お客さんからまだ支払ってもらっていない場合は、
計算上としては利益がドン出ていても、
手許にお金はありません。
これに対し、財産法の代表例は「相続税」です。
相続税は、死亡時の資産(現預金や不動産など)から
債務(借金など)を差し引きした「正味の財産」に対して
課税されます。
(基礎控除などの存在は説明の簡便上、割愛します)
よって、
大豪邸に住んでいても
多額の借金を背負っていれば、
相続税はかからないか、
あるいは、極めて少額となります。
つまり、
「実際の財布の状況を見る」というのが財産法です。
ですから、
「利益が出ているのになんでこんなにお金が残っていないのだろう?」
と思われる方は、
肌感覚としては「財産法」で考えてしまっているので、
法人税や所得税が準拠する「損益法によって算出された利益」が
しっくりきていないのです。
利益が出ているから、という理由で
法人税や所得税を払わないとイケナイってか!!
どうも解せない・・・。
こういったご経験・ご感想を持っておられる方は
結構多いのではないかと思います。
この「どうも解せない」という感情は、
「損益法」という考え方と
「財産法」という考え方との【違い】に
その端を発します。
損益法の代表例は
会社が払う法人税や個人事業主が払う所得税です。
法人税法や所得税法は
売上から経費を差し引いた利益に対して
課税する仕組みになっています。
よって、極端な話、
100億円の売上があったとしても、
その売上の全額がツケ(売掛金といいます)になっていて、
お客さんからまだ支払ってもらっていない場合は、
計算上としては利益がドン出ていても、
手許にお金はありません。
これに対し、財産法の代表例は「相続税」です。
相続税は、死亡時の資産(現預金や不動産など)から
債務(借金など)を差し引きした「正味の財産」に対して
課税されます。
(基礎控除などの存在は説明の簡便上、割愛します)
よって、
大豪邸に住んでいても
多額の借金を背負っていれば、
相続税はかからないか、
あるいは、極めて少額となります。
つまり、
「実際の財布の状況を見る」というのが財産法です。
ですから、
「利益が出ているのになんでこんなにお金が残っていないのだろう?」
と思われる方は、
肌感覚としては「財産法」で考えてしまっているので、
法人税や所得税が準拠する「損益法によって算出された利益」が
しっくりきていないのです。
「勘定合って銭足らず」が起こる原因
まず、売掛金や受取手形(電子記録債権)の存在が挙げられます。
売上代金が掛けですぐもらえなかったり、
受取手形(電債)により数か月先にならないと入金されなかったりすると、
売上は計上されて利益は出ているのにお金はナイ状態になります。
逆のことも言え、仕入れ代金をすぐに支払わず、ツケにしてもらったり、
あるいは支払手形(電子記録債務)を振り出して支払いを先延ばしにすると、
仕入と言う経費は発生してその分利益は減少するのに、お金は減っていません。
2点目に借入金の返済の存在です。
借入金は貸借対照表の「負債の部」における
代表的な勘定科目の1つですが、
借入れをしたときに売上にはならないように、
返済した時も経費ではありません。
あくまでも、借入によって(お金と共に)負債が増え、
返済によって(お金と共に)負債が減少する、ということなのです。
よって、仮に現金商売だとして、
つまり、売上も仕入・経費もカケ取引のない現金取引だったとして、
その場合に1か月の利益が100発生したとしも、
借入返済を80すれば、お金は20しか残りません。
しかし、損益計算上の利益は100のままです。
逆に言えば、売上がゼロの月であったとしても、
その月に銀行から100の借入をすれば、
利益は一切計上されていないのに
お金は100増えます。
3点目は、個人事業主の場合の話ですが、
「事業主貸」という存在です。
事業主貸の代表例は「生活費」です。
生活費は経費にはなりませんから、
損益計算書には出てきません。
(貸借対照表の資産の部に登場します)
よって、利益が100しか出ていないのに、
生活費を80出すとお金は20しか残りません。
4点目は、法人契約の生命保険の資産計上額です。
全額損金タイプの保険であれば
経費の額と出ていくお金の額は一致しますが、
解約返戻金があるタイプの定期保険などにおいては、
全額が経費に落ちず、
「6割資産計上、4割損金」という具合で、
経費に落ちる額と実際にお金が出ていく額とが一致しません。
つまり、お金としては100出ていったのに、
経費としては40しか計上されない、ということです。
5点目としては、固定資産の取得が挙げられます
仮に500万円の営業車をキャッシュで購入した場合、
出ていくお金は500なのに
減価償却費として経費計上される金額は
耐用年数のうちの1年分です。
耐用年数が経過しないと償却(経費化)できません。
(なお、土地は償却できないので、1円の経費にもなりません)
これら5点以上にも、
前渡金・貸付金・立替金・仮払金・保証金などのように、
お金は出て行っても、損益計算上の経費とならないものが
実務上の取引においては多々あります。
いかがでしょうか?
「利益は出ているのに、なんでお金は残っていないの?」
という悩み・疑問をお持ちの方は、
こういう視点からも決算書や試算表を
見直してみてくださいね。

【最後に言わせてチョーダイ】
「キャッシュフロー計算書」が重視されるのは、
このような<利益とお金の動きの不一致>の原因を
探るためでもあります。
しかし、キャッシュフロー計算書が分からなくても、
ご紹介したようなポイントを知っておくだけでも、
利益は出ているのになんでお金が無いの???
ってモヤモヤは大幅に軽減されますよ。
受取手形(電債)により数か月先にならないと入金されなかったりすると、
売上は計上されて利益は出ているのにお金はナイ状態になります。
逆のことも言え、仕入れ代金をすぐに支払わず、ツケにしてもらったり、
あるいは支払手形(電子記録債務)を振り出して支払いを先延ばしにすると、
仕入と言う経費は発生してその分利益は減少するのに、お金は減っていません。
2点目に借入金の返済の存在です。
借入金は貸借対照表の「負債の部」における
代表的な勘定科目の1つですが、
借入れをしたときに売上にはならないように、
返済した時も経費ではありません。
あくまでも、借入によって(お金と共に)負債が増え、
返済によって(お金と共に)負債が減少する、ということなのです。
よって、仮に現金商売だとして、
つまり、売上も仕入・経費もカケ取引のない現金取引だったとして、
その場合に1か月の利益が100発生したとしも、
借入返済を80すれば、お金は20しか残りません。
しかし、損益計算上の利益は100のままです。
逆に言えば、売上がゼロの月であったとしても、
その月に銀行から100の借入をすれば、
利益は一切計上されていないのに
お金は100増えます。
3点目は、個人事業主の場合の話ですが、
「事業主貸」という存在です。
事業主貸の代表例は「生活費」です。
生活費は経費にはなりませんから、
損益計算書には出てきません。
(貸借対照表の資産の部に登場します)
よって、利益が100しか出ていないのに、
生活費を80出すとお金は20しか残りません。
4点目は、法人契約の生命保険の資産計上額です。
全額損金タイプの保険であれば
経費の額と出ていくお金の額は一致しますが、
解約返戻金があるタイプの定期保険などにおいては、
全額が経費に落ちず、
「6割資産計上、4割損金」という具合で、
経費に落ちる額と実際にお金が出ていく額とが一致しません。
つまり、お金としては100出ていったのに、
経費としては40しか計上されない、ということです。
5点目としては、固定資産の取得が挙げられます
仮に500万円の営業車をキャッシュで購入した場合、
出ていくお金は500なのに
減価償却費として経費計上される金額は
耐用年数のうちの1年分です。
耐用年数が経過しないと償却(経費化)できません。
(なお、土地は償却できないので、1円の経費にもなりません)
これら5点以上にも、
前渡金・貸付金・立替金・仮払金・保証金などのように、
お金は出て行っても、損益計算上の経費とならないものが
実務上の取引においては多々あります。
いかがでしょうか?
「利益は出ているのに、なんでお金は残っていないの?」
という悩み・疑問をお持ちの方は、
こういう視点からも決算書や試算表を
見直してみてくださいね。

【最後に言わせてチョーダイ】
「キャッシュフロー計算書」が重視されるのは、
このような<利益とお金の動きの不一致>の原因を
探るためでもあります。
しかし、キャッシュフロー計算書が分からなくても、
ご紹介したようなポイントを知っておくだけでも、
利益は出ているのになんでお金が無いの???
ってモヤモヤは大幅に軽減されますよ。
関連エントリー
-
 連続税務小説 ヤマゲン 第27話「“税務調査が来る会社”の特徴」
ヤマゲンは、 珍しくポッキーに手を伸ばさなかった。 ネクタイのイチゴ柄だけが、 やけに目に入る。「田中さん」
連続税務小説 ヤマゲン 第27話「“税務調査が来る会社”の特徴」
ヤマゲンは、 珍しくポッキーに手を伸ばさなかった。 ネクタイのイチゴ柄だけが、 やけに目に入る。「田中さん」
-
 連続税務小説 ヤマゲン 第28話「“税務調査を呼ばない会社”の作り方」
ヤマゲンは、 売上表でも 決算書でもなく、 試算表を机に広げた。「田中さん」 ネクタイのイチゴ柄を、 指で軽
連続税務小説 ヤマゲン 第28話「“税務調査を呼ばない会社”の作り方」
ヤマゲンは、 売上表でも 決算書でもなく、 試算表を机に広げた。「田中さん」 ネクタイのイチゴ柄を、 指で軽
-
 連続税務小説 ヤマゲン 第29話「“税務調査が来ても慌てない会社”の共通点」
ヤマゲンは、 珍しく何も説明せず、 コーヒーを一口飲んだ。 イチゴポッキーも、 まだ開けない。「田中さん」 静
連続税務小説 ヤマゲン 第29話「“税務調査が来ても慌てない会社”の共通点」
ヤマゲンは、 珍しく何も説明せず、 コーヒーを一口飲んだ。 イチゴポッキーも、 まだ開けない。「田中さん」 静
-
 連続税務小説 ヤマゲン 第30話「税務調査が終わったあとに“必ずやるべきこと”」
税務調査が終わった翌日。 田中 恒一は、 何もない事務所で、 一人、机に向かっていた。 調査官はいない。 書類
連続税務小説 ヤマゲン 第30話「税務調査が終わったあとに“必ずやるべきこと”」
税務調査が終わった翌日。 田中 恒一は、 何もない事務所で、 一人、机に向かっていた。 調査官はいない。 書類
-
 連続税務小説 ヤマゲン 第31話 「青色申告を、甘く見た日」
月末の夕方。 田中 恒一は、工場の電気を一つずつ落としていた。 機械の音が止まり、 静けさが戻る。 その静け
連続税務小説 ヤマゲン 第31話 「青色申告を、甘く見た日」
月末の夕方。 田中 恒一は、工場の電気を一つずつ落としていた。 機械の音が止まり、 静けさが戻る。 その静け
竹岡税務会計事務所
経営が見えない!を数字でクリアに。
まずは、お気軽に無料相談を。
電話番号:090-7499-8552
営業時間:10:00~19:00
定休日 : 土日祝
所在地 : 大阪府富田林市須賀1-19-17 事務所概要はこちら